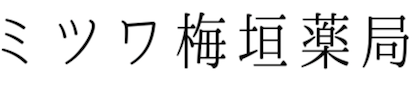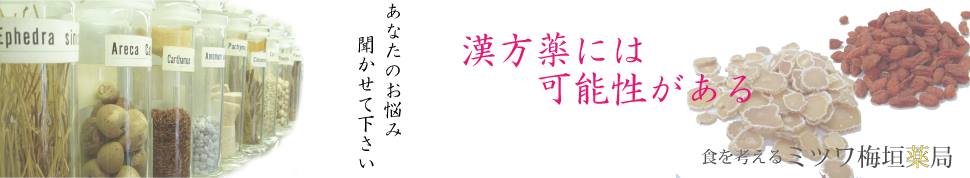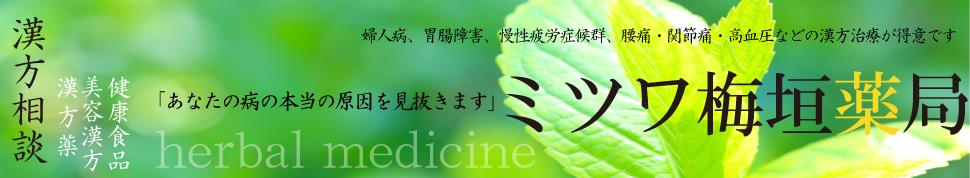現代では、甘いものを手軽に楽しめる環境が整っています。しかし、東洋医学の視点から見ると、過剰な甘いものの摂取は、健康にさまざまな悪影響を及ぼすと考えられています。本記事では、甘いものが私たちの体にどのような影響をもたらすのかを東洋医学の視点で解説します。
1. 甘味と五行の関係
東洋医学では、「五味(ごみ)」という考え方があり、食べ物の味は「酸・苦・甘・辛・鹹(しおからい)」の五つに分類されます。その中で「甘味」は、五臓の「脾(ひ)」に関係が深いとされています。
脾は消化・吸収を担い、気(エネルギー)を生成する重要な臓器です。適度な甘味は脾を養い、消化機能を助けるとされています。しかし、過剰な甘味の摂取は脾の働きを弱め、体に悪影響を及ぼします。
2. 甘いものがもたらす悪影響
① 脾の機能低下と「湿邪(しつじゃ)」の蓄積
甘いものを摂りすぎると、脾の機能が低下し、体内の「湿邪(余分な水分や老廃物)」が溜まりやすくなります。これにより、
- むくみ
- 消化不良
- 下痢や便秘
- 倦怠感 などの症状が現れやすくなります。
② 血の巡りの停滞(瘀血:おけつ)
過剰な甘味は血の巡りを悪くし、「瘀血(おけつ)」という状態を引き起こします。瘀血が進むと、
- 頭痛や肩こり
- 冷え性
- くすみやシミなどの肌トラブル
- 生理不順やPMSの悪化 といった症状が現れます。
③ 気の停滞と精神の不安定
甘いものは一時的に気分を高揚させますが、その後急激にエネルギーが落ちるため、
- イライラや不安感
- 集中力の低下
- 眠気やだるさ といった症状を引き起こします。
甘いものは天然もものであろうが、はちみつ、ほしいも、果物でも同じです。たまに果物を食べるなどすることは否定しませんが、多くの方が、なにかしら毎日甘いものを食べているのが現状ですので、是非、気をつけていただきたいです。