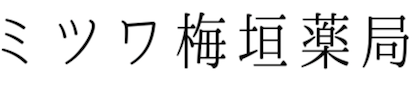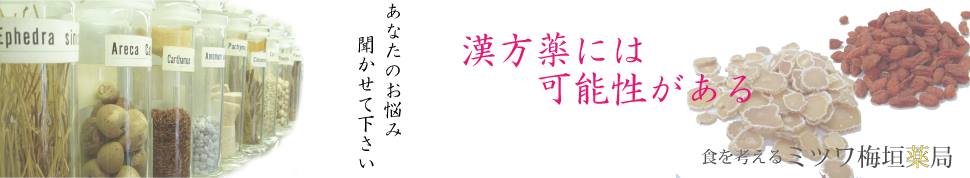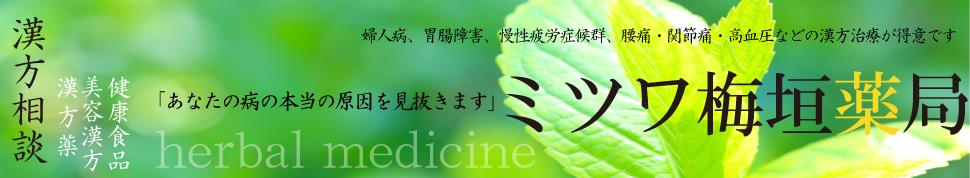めまいは現代医学では三半規管の異常や自律神経の乱れなどが原因とされていますが、東洋医学の視点では「気・血・水(き・けつ・すい)」のバランスの乱れが主な要因と考えられています。今回は、東洋医学的にめまいの原因と対策について解説します。

1. めまいの主な原因
東洋医学では、めまいは以下のような原因で起こるとされています。
① 気虚(ききょ) 気(エネルギー)が不足すると、頭に十分なエネルギーが巡らず、ふらつくようなめまいが起こります。疲れやすい、顔色が青白い、息切れしやすいといった症状を伴います。
② 血虚(けっきょ) 血が不足すると、脳に必要な栄養が供給されず、立ちくらみのようなめまいを引き起こします。目のかすみ、動悸、不眠、肌の乾燥なども特徴的な症状です。
③ 水滞(すいたい) 体内の水分バランスが崩れると、耳の奥や脳に不要な水分が溜まり、ぐるぐる回るようなめまいが起こります。これは「痰湿(たんしつ)」と呼ばれ、むくみや吐き気を伴うことが多いです。
④ 肝陽上亢(かんようじょうこう) ストレスや怒りによって肝のエネルギーが過剰に上昇すると、頭部の血流が異常になり、めまいが発生します。頭痛やイライラ、不眠を伴うことが多いです。
- 2.対策
- 規則正しい生活を心がけ、睡眠を十分に取る。
- ストレスを減らすために、適度な運動や深呼吸を行う。
- 体を冷やさないようにし、血流を改善する。
東洋医学では、めまいを単なる症状としてではなく、体のバランスの乱れとして捉えます。日常生活の中で気・血・水の流れを意識し、健康な状態を維持することが大切です。