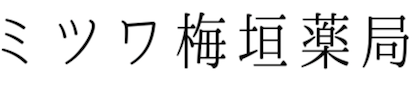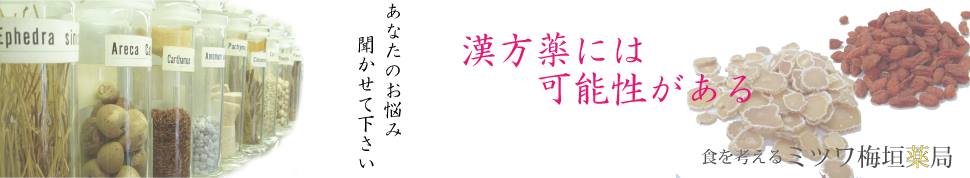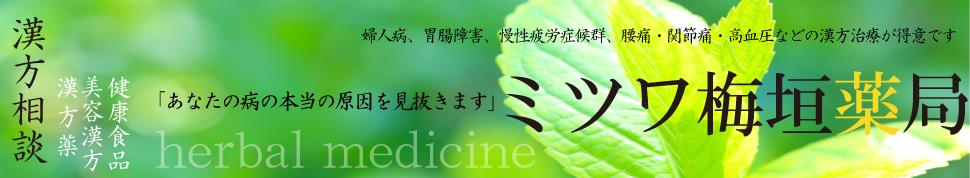東洋医学では、体内の水分バランスが乱れることを「水滞(すいたい)」と呼びます。この水滞が特に起こりやすい季節は梅雨や夏、秋の長雨の時期です。
1. 水分代謝異常が起こりやすい季節
- 梅雨:湿気が多く、体内の余分な水分が排出されにくくなるため、水滞が起こりやすい。
- 夏:冷たい飲み物の摂取やクーラーの影響で、体内の水の巡りが悪くなる。
- 秋の長雨:湿度が高いと体に湿気が溜まり、特に胃腸の働きが低下しやすい。
2. 水滞による症状
- 頭重感やめまい:脳や耳の周りに水分が滞ることで、ぼんやりした感覚や回転性のめまいが起こる。
- むくみやすい:水分が体に溜まり、特に足や顔がむくみやすくなる。
- 消化不良や胃もたれ:湿気によって脾(胃腸)の機能が低下し、食欲不振や胃もたれが生じる。
- だるさや疲れやすさ:体内の水分が適切に排出されないと、気の巡りが悪くなり、倦怠感を感じる。
3. 水分代謝を改善する対策
-
- 生活習慣:
- 冷たい飲み物を控え、温かい飲み物を摂る。
- 湿気の多い日は、除湿をしながら過ごす。
- 軽い運動で汗をかき、余分な水分を排出する。
- 生活習慣:
東洋医学では、季節によって体調が変化することを重視します。特に湿気の多い時期には、水分代謝を意識した生活を心がけ、健康を維持しましょう。